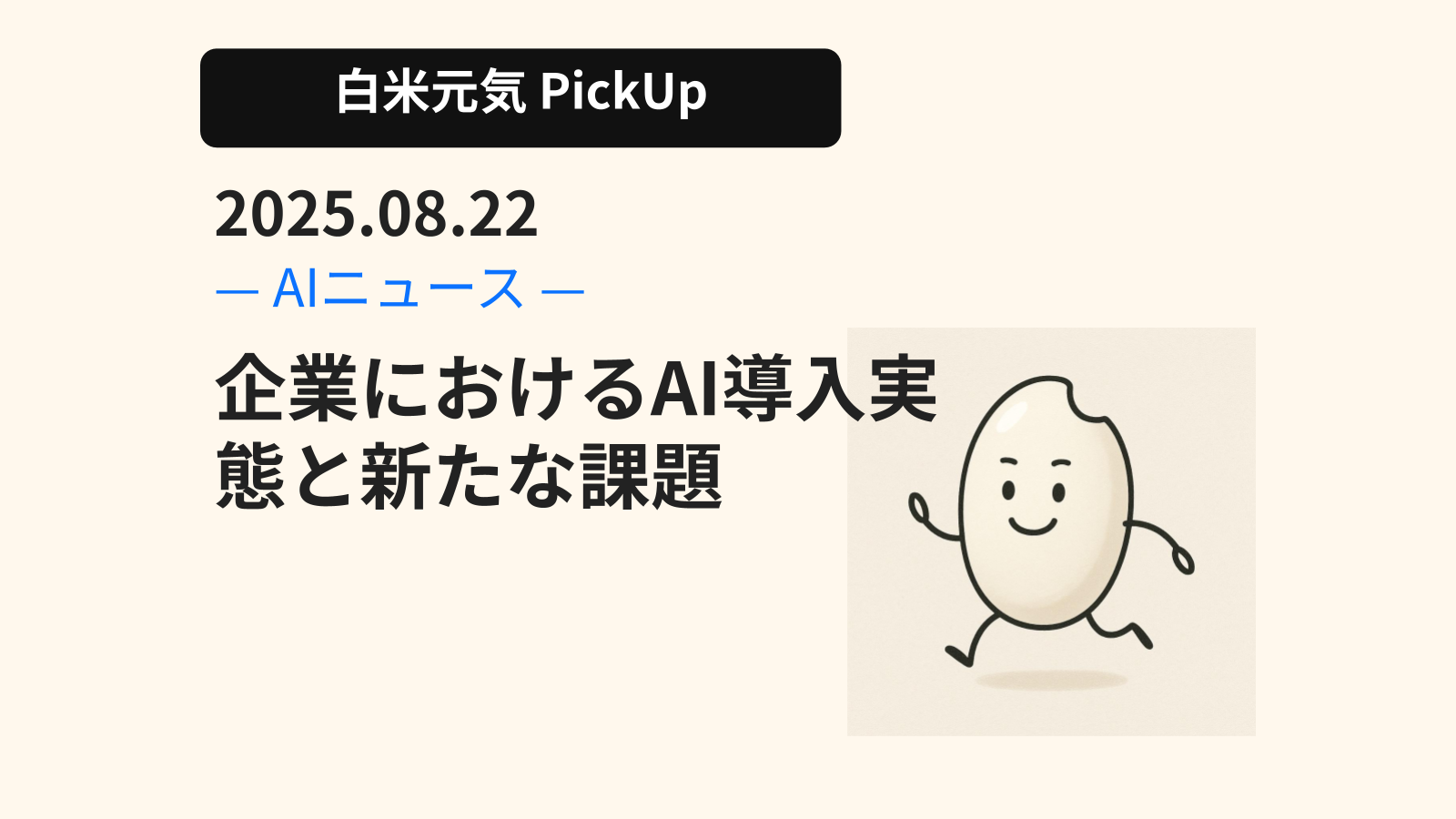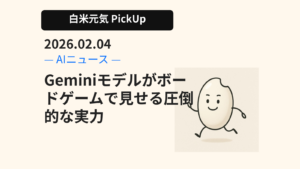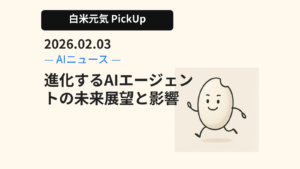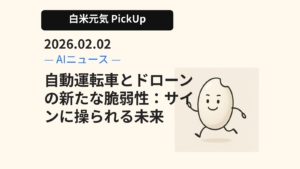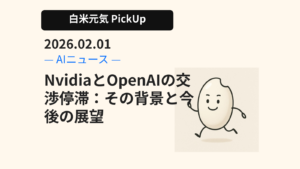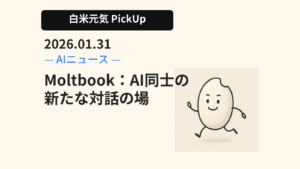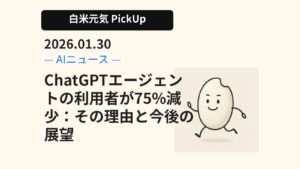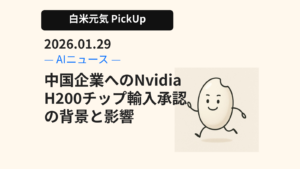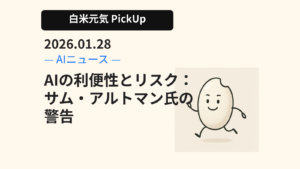執筆:白米元気
MITが発表した最新の報告書では、企業における生成AIの導入に関するさまざまな誤解が浮き彫りとなっています。特に驚くべきは、95%のパイロットプロジェクトが失敗したとされる中で、実際には従業員たちが個人のAIツールを積極的に活用し、その結果、業務に対する影響が非常に大きいことです。これにより、企業内でのAI導入が見えにくくなっている現状があります。
従業員によるAI活用:公式ツールとの乖離
MITのプロジェクトNANDAから発表されたこの報告書によれば、90%もの従業員が個人的なAIツールを使用して仕事を進めている一方で、公式なAIサブスクリプションを持つ企業はわずか40%にとどまっていることが示されています。このデータから、多くの企業内で「シャドーAI経済」が形成されていることが明らかになりました。具体的には、従業員たちはChatGPTやClaudeといった消費者向けのツールを使用し、日常的な業務をサポートしています。特にある企業においては、弁護士が高額な契約分析ツールよりもChatGPTを利用することで、より高品質な成果物を得ているとのことです。このような傾向は多様な業界で見受けられ、企業システムは「脆弱」や「過剰設計」と評される一方で、消費者向けツールは「柔軟性」や「即効性」において高い評価を受けています。
成功事例の背景:新たな視点から見るAI導入
この報告書では、企業が内部でAIを構築しようとする試みが失敗する理由として、「学習能力」の欠如が挙げられています。多くの企業向けAIシステムはフィードバックを保持せず、またコンテキストに適応できないためユーザーから不満が生じることが多いのです。それとは対照的に、消費者向けツールはその応答性や柔軟性から高く評価されています。その結果として、多くの従業員は簡単なタスクにはAIを選ぶ傾向があります。このシャドー経済では、生産性向上が見えづらくなっていますが、実際には従業員たちが日常業務を効率化していることも明らかになっています。また報告書によると、一部の企業はこの流れに注目し始めており、個人使用から学びながら価値あるツールを特定しようとしているようです。さらに、AIスタートアップとの外部パートナーシップは成功率67%という高い数字を示しており、自社開発よりも効果的であることも明らかになっています。
まとめ:見えない成功と今後の展望
このMIT報告書から得られる主なポイントとして挙げられるのは、企業内で生成AIが静かに成功しているという事実です。従業員たちは適切なツールを利用することで生産性を向上させており、その成果は公式な指標には表れづらいものとなっています。このような状況下では、企業側も新たな視点からアプローチし、自社に最適なツール選びやパートナーシップ構築を行う必要があります。今後もこのトレンドは続くと考えられますので、多くの企業がこの波に乗り遅れないよう注意深く動いていくことが求められるでしょう。